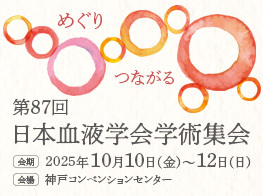このたび、2025年2月22日から23日の日程で横浜において開催された、Highlight of ASH in Asia-Pacific (HOA) に参加する機会を得ましたので、ご報告いたします。HOAは本年も2日間のプログラムで開催されましたが、前日の2月21日には米国血液学会主催で、臨床研究遂行に必要な知識のブラッシュアップを目的とした、若手研究者向けの集中レクチャー (ASH Clinical Research Trainee Day) が実施され、こちらにも参加させていただいたため、計3日間の日程となりました。
ASH Clinical Research Trainee Dayでは、午前中は各領域のエキスパートからのミニレクチャーが、午後からは具体的な臨床疑問に対して、それを解決するための臨床試験をどのように立案するかというテーマで、グループワークが行われました。
ミニレクチャーでは、まずDr. Walkerから、リサーチクエスチョンを定式化しどのように臨床試験に落とし込むか、実例を通じてわかりやすい解説がありました。Mrs. Veselyからはデータマネージャーの立場から、EDC構築の最適化におけるコツを学びました。具体的には、入力項目は必要最小限にすること、EDC構成を工夫することで、入力者の負担を減らすことが、質の高いデータ収集につながるという重要なメッセージがありました。数多くのミニレクチャーの中で特に印象に残ったのは、Dr. Cukerによるメンターシップの講義でした。メンター/メンティーシップは与え・与えられるという一方向の関係ではなく、双方向の関係であるというメッセージのもと、メンター/メンティーシップを実りあるものとするためのtipsを、実例をもとに楽しく解説されました。Dr. Cukerの講義を拝聴し、自分自身向上すべき点が多々あることに気付かされたのと同時に、メンター/メンティーシップといった領域についても、言語化して系統的に講義を行うことの素晴らしさを感じました。私もtraineeと言いづらい年次になってきましたが、このような系統的なミニレクチャーで臨床試験における知識が整理できました。同時に、アジア各地域から参加しているメンバーの熱量を感じ、アジアでのコラボレーションの可能性を実感しました。
午後からグループワークでは、Dr. ReshelfとDr. Hoのもと、”Should patients with MM receive bispecific antibodies (BsAbs) as part of their induction chemotherapy?” という臨床疑問を題材に、至適な試験デザインを8人程度のメンバーでディスカッションしました。各国でBsAbsの承認状況が異なるものの、いずれのメンバーも熱量が高く、それぞれの実診療における臨床疑問を踏まえた濃密な議論が展開されました。ディスカッションの後のフリートークでは、多発性骨髄腫における新薬開発動向が話題となり、基礎研究と臨床開発の両輪がうまくワークしている米国の状況を垣間見ることができました。
翌日からの2日間で開催されたHOAでは、ASH2024で報告された重要演題を、各領域のエキスパートがコンデンスしてその臨床的意義の考察とともに紹介するものです。ASHでは膨大な演題数のため、重要演題を網羅することが難しいことが多々ありますが、HOAでは最新の研究結果を効率よく把握することができました。時に、普段の学会では聴講する機会の少ない良性疾患の治療パラダイムをアップデートすることができました。
末筆になりますが、HOA参加に際して種々のサポートをくださいました天野様をはじめとした日本血液学会の皆様、さらに快く私を送り出してくださったがん研究会有明病院 血液腫瘍科メンバーに心より感謝申し上げます。