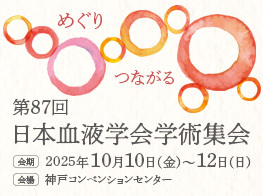この度、JSHからの派遣を受け、横浜で開催された2025 Highlights of ASH (HOA) in Asia-Pacificに参加してきました。HOA最終日の夜にこの原稿を書こうと思いましたが、静かな興奮が治まらず、一晩落ち着いてから書き始めています。私は一度だけASHに参加したことがあるのですが、今回はその時と同じ興奮を覚えました。読んで頂いている方に、この熱量が少しでも伝わればと思います。
JSHからの派遣でHOAに参加すると、会期前日のClinical Research Trainee Day (CRTD)から参加することになります。私は大学院4年生で、Traineeと言えるのも最後かと思い、今年の派遣を希望しました。大学院の卒業が迫り、様々な提出物の期限や実験が立て込む中で、日本開催であったことも参加の後押しとなりました。CRTDでは臨床研究のいろはを系統的に学ぶことができます。研究テーマの立案、研究デザインの設定、データベースの作成、論文投稿のtipsなど、今まで何となくやってきたことを言語化して説明してもらうことで、新たな気付きをいくつも得ることができました。これまで後方視的研究でデータセットを扱った経験があったおかげで、より多く学べたように感じました。投稿時の” Journal Selection” については” Aim high!” とのことで、そのようなマインドで良いのだという自信になりました。また” Aim high!” の次には” Handling Rejection” があり、Rejectionについて自分のことではなく、一歩引いた視点で学ぶことができたのは貴重な経験でした。
CRTDの中で、最も大きな(特に心理面の)ウェイトを占めるのはグループディスカッションではないでしょうか。今年は、各国の参加者が小グループに分かれ、グループ毎にResearch Question (RQ)が与えられました。私たちのグループに与えられたのは「多発性骨髄腫の寛解導入療法にteclistamabやelranatamabを用いるべきか」というRQでした。このRQの答えについて意見を述べ合うのではなく、このRQの答えを明らかにするために行う臨床試験のプロトコールについて、ファシリテーターの先生やグループメンバーと共に考えました。緊張の中でこの時間を迎えましたが、終わって振り返ってみると、病院実習のクルズスのような雰囲気だったと感じています。前向き試験の組み立てを考えるのは初めてで、非常に新鮮でしたし、盲検化の有無やアーム数の設定、どのような情報を元に症例数を見積もるかなど、実現可能性を考慮したプロトコールを組み立てていく過程を知ることができました。今後、前向き試験についてこれまでとは違った視点で見ることができるのではないかと思います。一方で、臨床試験を計画して実際に行う将来の姿が今の私からは想像出来ず、自分自身には後方視的研究の経験しかないことをファシリテーターの先生に相談してみました。すると「前向き試験を考える上でも、後方視的研究の経験は生きる。実際に自分が臨床試験を初めて行ったのは40歳を過ぎてからだった。あなたはまだまだ若いから大丈夫。」とのお答えを頂き、少々安心しました。HOAに参加されていた講師の先生は、各分野のエキスパートでありながら非常にフレンドリーで、1を聞くと10を返して下さるので、質問もしやすかったです。
CRTDが終わり、一番のヤマを超えたと思っていましたが、2日目からのHOAがこれほどにも濃密であることは想像もしていませんでした。HOAでは、ASHでの研究報告を掻い摘んで、疾患別にまとめて講師の先生が説明して下さいます。それぞれの研究が、今のstandard of careのどの点を変えるものなのか、次の課題は何か、残されているアンメットニーズは何かなどについて、オーバービューしながらいくつかの研究にフォーカスしていく流れでした。今ASHでアツい点を、各分野で満遍なく知ることができるというのがHOAの大きな魅力であると感じました。ただし注意しなければいけないのはプレゼンテーションのスピードです。英語に慣れている方であれば問題はないと思うのですが、膨大な情報量がものすごいスピードで目と耳から入って来ます。体感としては、英語のリスニング教材を1.5〜2倍速で聞き続けている印象でした。現代で重視されるタイムパフォーマンスという観点では素晴らしいものでしたが、私にはとても早過ぎて、最後のセッションが終了した時にはもうふらふらでした。しかしながら、視覚情報も駆使して、しっかり情報を受け取ろうという姿勢は最後まで保てたと思います。
HOAではLunch with the Expertsというプログラムがあり、各分野のエキスパートとテーブルを囲んで食事をしながら、フランクに質問ができる機会があります。私は、CMLに関する臨床的な疑問点についてエキスパートオピニオンを聞いてみたかったので、Jorge Cortes先生のいらっしゃるテーブルを選びました。CMLではtreatment-free remissionが可能になりつつある中で、いつまでフォローアップしていくべきかという質問に対して、”Forever!” と力強くお答え頂いたのが印象に残りました。
総じて、講師の先生との距離感が近く、参加者も積極的な方が多いので、その流れに乗ってHOAを楽しむことができました。もっと英語ができればさらに様々な議論に加わることができたし、理解が深まったのは間違いないですが、それでも得られたものは大き過ぎました。なお、英語力に不安のある方は、グループディスカッションやLunch with the Expertsで講師の先生の隣に座ることをおすすめします。隣だと声も聞きやすいですし、質問するハードルも下がる気がしました。
最後になりますが、JSH理事長の高折先生、三谷先生、小川先生、丸山先生、前田先生、坂田先生、片岡先生には、HOA会期中に非常にお世話になりました。先生方から受けた薫陶を胸に、目標を高く持っていきたいと思いました。一緒にHOAに参加させて頂いた山内先生、寺本先生、長谷河先生、藤田先生、大島先生とは、短い会期中だったにも関わらず親しくさせて頂きありがとうございました。また推薦して下さった自治医科大学の神田善伸先生、事務局の天野さんをはじめとして、関係者の皆様に深く感謝致します。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)